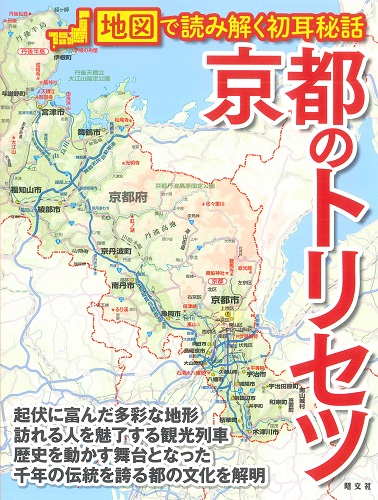目次
南北朝動乱が起こった背景
当時の朝廷内では、「持明院統(じみょういんとう)」と「大覚寺統(だいかくじとう)」という二大皇統が交互に皇位を継承するルールがありました。
大覚寺統の後醍醐天皇は、自分の血統による継承権の独占を狙い、ルールを決めた鎌倉幕府の打倒を計画します。幕府は皇位継承に大きな影響力をもっていたので、これを倒さない限り、皇統の独占は実現できないと考えたからです。
笠置山の戦いが起こる
最初の倒幕計画は、1324年9月に朝廷を監視する六波羅探題(ろくはらたんだい)が察知して失敗しました。1331年4月にも寺社や河内の土豪(諸説あり) 楠木正成(くすのきまさしげ)らと計画していましたが、仲間の密告により頓挫しました。天皇は幕府の追手を振り切り笠置山へと逃亡。そして同年9月、ついに挙兵したのです。
笠置山は戦いに有利だったが陥落
山腹にある笠置寺は山岳密教の修行道場となっており、巨石がいたるところに露出していました。50の寺院と僧兵が守るまさに要塞において、楠木正成らを含めた3000程度の天皇の軍は、崖と岩に囲まれた地形を活かした戦いで六波羅探題の部隊を翻弄。怪力の僧本性坊(ほんじょうぼう)は岩を投げつけて戦ったといわれます。予想外の苦戦により単独制圧は無理と判断した六波羅探題は、幕府に援軍を要請します。
これを受けて鎌倉幕府は御家人の足利高氏(のちの尊氏)を大将とする増援軍を派遣し、約7万5000の兵で笠置山を完全に包囲しました。そして9月28日、夜襲と放火で天皇の軍は総崩れとなり、逃亡した後醍醐天皇も大正池(井出町)のあたりで捕縛され、正成が逃げ込んだ赤坂城も10月21日に陥落しました。
笠置山の戦いの終結と鎌倉幕府の滅亡
後醍醐天皇は翌年3月に隠岐へと流され、側近も多数が処刑されます。しかし、武士の間で鎌倉幕府への不満が募り、天皇に加勢する勢力も増えていきました。そして1333年、鎌倉幕府は滅亡します。
倒幕を成した天皇はみずから政治を行いますが、ここからさらにゴタゴタは続きます。そして室町幕府の3代将軍・足利義満の時代まで、南北朝の争いは終わらない―と、ここまで笠置山の戦いを中心に歴史を振り返ってきました。1407年に笠置山の僧である貞繁(ていはん)が描いたとされる絵を江戸末期の浮世絵師・岡本春暉(おかもとしゅんき)が写した絵図は、当時の戦いの様子を示す貴重な資料とされます。
笠置山の戦いと南北朝動乱の真相はいかに
ところが、2020年に発刊された『椿井文書(つばいもんじょ)』(馬部隆弘(ばべたかひろ)著/中公新書)で衝撃の事実が明らかになり、周辺自治体を巻き込む騒動となりました。どうやらこの絵図は、偽文書にもとづき作成されたらしいのです。詳細はこの本に譲りますが、笠置山の戦いについての逸話は、何がどこまで本当なのかわからなくなってしまったのです。
笠置町と木津川町の複雑に入り組んだ謎の境界線
笠置町笠置地区と木津川市加茂町山田地区には、アメーバのように複雑に入り組んだ境界線が存在します。この周辺は、もともと入会地(複数の村が共有する土地)で、一部が私有地となっていました。明治維新で全国に市町村が設置された際、この入会地は所有者の住所(笠置町と加茂町)ごとに分けたことで、このような境界線ができあがったといわれます。
加茂町内には、ほかにも北地区、兎並(うなみ)地区、美浪(みなみ)地区などあちこちで境界線が入り組んでいます。

現地には入り組んだ山道と茶畑が広がっています。
『京都のトリセツ』好評発売中!
日本の各県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。京都の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。思わず地図を片手に、行って確かめてみたくなる情報を満載!
Part.1 地図で読み解く京都の大地
・京都府の4地形区と断層/京都盆地とその出入り口(逢坂と大山崎)
・琵琶湖疏水の秘密/洛中と洛外を隔てるおどい
・観光のメッカ東山の地形(地獄の入り口六道珍皇寺)
・失われた巨椋池/天橋立はなぜあのような地形になったのか
・舞鶴が重要港湾となった地形的な秘密
・霧のまち亀岡(亀岡盆地)
…などなど京都のダイナミックな自然のポイントを解説。
Part.2 京都を駆ける充実の交通網
・山城盆地を通る街道(東海道、中山道の終着地)
・若狭と京都を結ぶ「鯖街道」
・日本初の一般営業用電車が通った京都市電
・京都鉄道博物館
・梅小路
・京都の私鉄〇〇な阪急
・大赤字から復活した京都丹後鉄道
…などなど京都ならではの交通事情を網羅。
Part.3 京都の歴史を深読み!
・丹後に一大勢力が存在した証拠 三大古墳に埋葬された人々
・古代日本を支えた渡来人と京都の関係
・なぜ京都は都になったのか 恭仁京~平安京までの変
・南北朝動乱の始まり 笠置山の戦い
・信長、光秀、秀吉…みんな京都で死んだ
・幕末の騒乱の舞台となった京都
・近代化にいち早く着手!日本初の博覧会は京都の寺で開かれた
…などなど、激動の京都の歴史に興味を惹きつける。
Part.4 京都で育まれた産業や文化
・シンボル京都タワーと近代建築
・学問の都・京都の大学
・京料理とそれを支える伝統野菜
・「丹波」ブランドをめぐる攻防
・日本映画と京都
・「女酒」伏見の酒蔵
・王城の裏鬼門「男山」と岩清水八幡宮
…などなど京都の発展の歩みをたどる。
『京都のトリセツ』を購入するならこちら
※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。
皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!