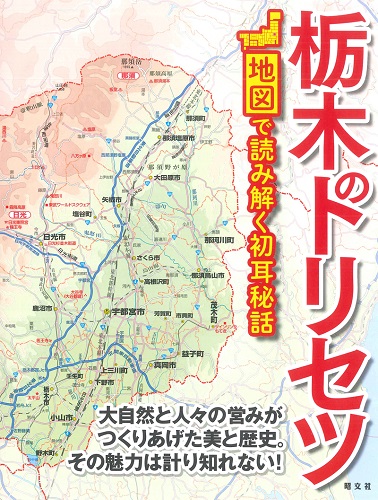目次
【栃木の織物】真岡木綿(真岡市)
たとえば、浴衣や手ぬぐいなどに使われる上質な木綿の生地を「特岡(とくおか)」と呼ぶのですが、実はこの言葉、真岡(もおか)市が由来となっているのはご存じでしょうか。江戸時代、真岡市とその周辺では綿の栽培が盛んでした。真岡で作られた木綿は、丈夫ながらも絹のような肌触り、染め上がりの加工技術にも優れ、「真岡」といえば木綿の代名詞として通じたほど、絶大なる人気を博しました。その名残で、真岡産のものでなくても上等な木綿のことを「特岡」と呼ぶようになったのです。
江戸の木綿問屋で扱われた木綿の6割が真岡木綿であったという記録が残ります。真岡市内にある「真岡木綿会館」には、栃木県伝統工芸士である機織り技術者が在籍。工程見学や機織り体験もできます。
栃木の織物:真岡木綿の衰退
しかし開国により、安価な輸入綿糸が流通し始めると真岡木綿は衰退し、戦後になるとほとんど生産されなくなりました。近年になり一世を風靡した真岡木綿の技術を後世に残そうと、1986(昭和61)年、真岡木綿保存振興会が発足、その技術を今に伝えています。
【栃木の織物】野州麻(鹿沼市)
園芸用の鹿か沼ぬま土で有名な鹿沼市は、「野州麻(やしゅうあさ)」の産地でもあります。麻は、古くから生活用具、また神社の神事など特別な行事にも用いられ、日本人の生活と文化を支えてきました。鹿沼市は知る人ぞ知る麻の生産日本一を誇る地域で、全国の麻の栽培面積の実に約7割を占めているのです。
古来、麻は神聖なものとされ、衣服などのほか神社の神具などに使用されてきました。野州麻は現在でも伊勢神宮の注連縄(しめなわ)や、横綱のまわしにも使われています。そのほか、野州麻を使ったコースターやバッグなどが作られ、「かぬまブランド」製品として、まちの駅などで販売されています。
栃木の織物:野州麻が存続の危機にさらされた事件
ひとつ、麻にまつわるエピソードがあります。昭和40年代、栃木県で麻薬にもなる麻の盗難が社会問題となり、野州麻は存続の危機にさらされました。地元農家の強い要望で、栃木県農業試験場鹿沼分場は10年の歳月をかけ、無毒麻「とちぎしろ」の開発に成功し、官民一丸となって危機を乗り越えてきた歴史があります。
【栃木の織物】結城紬(結城市)
徳川家康の「小山(おやま)評定」で知られる小山市周辺と茨城県の結城(ゆうき)市には、「結城紬(ゆうきつむぎ)」という奈良時代から続く織物があります。
栃木の織物:結城紬は江戸時代に町民の間で人気に
紬とは、もともと農家の人たちが、くず繭(まゆ)や汚れ繭を使って自分用に作った丈夫な野良着(のらぎ)を指しました。江戸時代、この地方の新しい領主となった伊奈備前守忠次(いなびぜんのかみただつぐ)が信濃(しなの)の上田から繊工を招き、新たな技法を導入したことでグレードアップし、以来、紬は高級織物となりました。軽くて丈夫、着れば着るほど味の出る結城紬は、贅沢禁止の規制が緩んだ江戸後期、裕福な町民の間に広まり人気となったのです。
栃木の織物:結城紬はユネスコ無形文化遺産
古くから伝わる技術を守りつつ、時代に合わせさまざまな意匠の作品を世に送り出している結城紬は、1956(昭和31)年に重要無形文化財に指定され、2010(平成22)年にはユネスコ無形文化遺産へ登録となりました。
重要無形文化財の指定要件でユネスコ無形文化遺産にも登録された、「糸つむぎ」「絣(かすり)くくり」「地機(じばた)織り」の技術をはじめ、工程のほとんどが手作業。なお「結城」は茨城県の地名ですが、平安時代末期以降、北関東に一定の勢力を保った「結城氏」に由来するという説が有力です。
【栃木の織物】足利銘仙(足利市)
大正末から昭和初期にかけて、女性たちの間で「銘仙(めいせん)」の着物が全国的なブームとなりました。銘仙はもともと「太織(ふとおり)」と呼ばれ、くず繭からとれた節糸(ふしいと)を用いて無地や縞(しま)などに先染めして織った着物を指しました。その後、きめ細かなという意味で「目千(めいせん)」と呼ばれ、もっと上品にと「銘仙」と表記されるようになりました。縞柄や矢絣(やがすり)が主流だった銘仙は、大正時代になると織りを工夫し、産地ごとに特色を出すようになります。伊勢崎・秩父・八王子・桐生と並ぶ5大産地のひとつ、足利産の「足利銘仙」の人気は高く、ピーク時の昭和初期には全国一の生産量を誇っていました。その裏には、イノベーション、コストダウン、プロモーションといった、独自の販売戦略がありました。
栃木の織物:足利銘仙の魅力とは?
まず、型紙を使って直接糸に型染できる「模様銘仙」の技法によって、足利銘仙は曲線的なデザインや幾何学的なデザインを可能としました。また、それまで職人が考えていた図案を、今でいうデザイナーという組織となって行うことにより、自由奔放なデザインが次々と生み出されるようになります。この大胆な花模様や抽象模様の着物に、当時の流行に敏感なモダンガールたちは飛びつきました。さらに力織機(りきしょっき)を取り入れたことにより、大量生産のための合理化が可能となったのです。そのため価格は手頃なものとなり、折しも社会進出を始めた女性たちのニーズを満たしました。

足利市の中心部を渡良瀬川が流れ、北岸をJR両毛線、南岸を東武伊勢崎線が走ります。足利銘仙最盛期の昭和初期には、足利地方の織戸数は大小合わせ2000軒近くありました。
栃木の織物:足利銘仙の広告展開
そして特筆すべきはその宣伝力です。一流画家や有名女優を起用したポスターを制作し、三越や髙島屋といった百貨店と連携して、国内外へ足利銘仙のブランドを発信しました。こうした取り組みは足利織物産業特有のものです。
足利市中心部付近足利銘仙を着た美人画を山川秀峰(しゅうほう)や北野恒富(つねとみ)など、当代一流の日本画家に依頼し、ポスターや絵葉書にして全国展開を図りました。今でいうマーケティングやプロモーションにあたる手法は、当時としては画期的でした。
足利銘仙をはじめ栃木の織物が発展した背景

足利織物の最初の記録は奈良時代のもので、一般に広まったのは渡良瀬川の舟運が発達した江戸時代です。そして、大躍進を遂げたのは明治時代。足利の織物業者たちは時流を読み、既存の綿から絹織物の大量生産へと転換を図ります。品質向上と生産力アップのための技術革新と機械化、さらに管理・教育体制の強化。そうして自らの力で、足利織物のブランド力と輸出量を拡大していったのです。
織物とともに生きた足利人の独立独歩の精神は、1885(明治18)年の織物講習所(県立足利工業高校の前身)の設置、1888(明治21)年の両毛(りょうもう)鉄道の敷設(のちに国有化、現在のJR両毛線)や、1895(明治28)年の足利銀行の設立を実現し、地域経済の近代化を大きく推し進めたのです。
『栃木のトリセツ』好評発売中!
地形、交通、歴史、産業…あらゆる角度から栃木県を分析!
栃木県の地形や地質、歴史、文化、産業など多彩な特徴と魅力を、地図を読み解きながら紹介するマップエンターテインメント。栃木の知っているようで知られていない意外な素顔に迫ります。地図を片手に、思わず行って確かめてみたくなる情報満載!
Part.1 地図で読み解く栃木の大地
・雷が多い理由は地形にあり!
・奥日光は男体山がつくった?
・日本最大の渡良瀬遊水地ができた理由
・川を横切る川!? 不毛の扇状地を潤す那須疏水
・奈良の大仏に那須の金!? 栃木は地下資源の宝庫だった!
・F.L.ライトが山ごと買った大谷石の魅力
・葉脈から動物の体毛までくっきり! 古塩原湖に眠る太古の記憶
・栃木にゾウやサイがいた! 化石と野州石灰の産地・葛生
Part.2 栃木を走る充実の交通網
・県南を通る予定だった!? 東北本線の紆余曲折
・日本のマンチェスターを目指せ! 織物の街をつなぐ両毛線
・栃木随一の観光地をめぐるJR日光線と東武日光線の軌跡
・地域の産業を牽引した人車鉄道/郷愁誘う各地の廃線をたどる
・わたらせ渓谷鐵道の前身は足尾鉄道
・幾多の苦難を乗り越えた真岡線
・構想から25年を経て着工! 宇都宮~芳賀にLRTが走る
・要衝・下野国を貫く街道の変遷
・舟運で“蔵の街”となった栃木市
Part.3 栃木で動いた歴史の瞬間
・なぜ「那須」が付く市や町が多い?
・遺跡からたどる東山道と律令期の下野国
・平将門を討った豪傑・藤原秀郷とは何者か?
・足利氏には2つの流れがあった! 鎌倉幕府と下野御家人の関係
・名族宇都宮氏の栄枯盛衰
・ザビエルやフロイスも讃えた「坂東の大学」足利学校
・江戸幕府最大の聖地・日光東照宮創建
・廃藩置県、そして栃木県誕生!
・「一の宮」が2つ? 日光二荒山神社と宇都宮二荒山神社
・不毛の原野が酪農王国に! 那須野が原の大開拓
Part.4 栃木で生まれた産業や文化
・木綿、紬、絹織物、麻…栃木は織物の名産地
・益子焼が始まってまだ170年足らず? 益子が「陶器の里」になったわけ
・半世紀にわたって生産量日本一!! 栃木はなぜいちご王国になった?
・関東平野が工業誘致にぴったりだった? 宇都宮は新たなものづくり都市へ
・「それって栃木?」県名抜きで知名度の高い観光名所
『栃木のトリセツ』を購入するならこちら
※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。
皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!